「最近老化を感じるけど、まだ若返りたい」と思う方へ。
私がアンチエイジングに興味を持つきっかけになったのが、ダニーデン研究(Dunedin Study)という世界的な長期研究でした。
この研究は、「人は同じ年齢でも老化のスピードが違う」ことを科学的に証明しています。
理学療法士として、この知見をどう日々の健康づくりに活かせるのかをお伝えします。
ダニーデン研究とは?世界が注目する「老化のスピード」研究
1000人を20年追跡した長期研究
ダニーデン研究とは、ニュージーランド南島のダニーデン市で1972年~1973年に誕生した約1000人を26歳から45歳までの20年間追跡して、老化の状況を調べた研究です。老化は個人差が大きく、生活習慣、環境に大きく左右されることが示唆されています。
生物学的年齢と歴年齢
生物学的年齢とは、太陽の周りを回った公転回数で決まる暦年齢とは異なり、生物の機能的な年齢のことを言います。生年月日が全く同じ人間であっても、「見た目年齢」「カラダ年齢」は全く異なります。私の周りや近所の親世代の方々、日々リハビリに来院している患者さん達をみていると色々と感じる事があります。みなさんのまわりの方にも色んな方がいると思います。若くみえる、老けて見える。これに理由があるとは…。
ダニーデン研究により、生物学的な老化の速度には大きな個人差があることが判明しました。最も遅い人では1年の暦年齢に対して0.40年の生物学的な老化しか進まない一方、最も速い人では2.44年もの生物学的な老化が進んでいました。…マジですか笑。衝撃。そりゃ同窓会で20年ぶりに会った同級生が誰だかわからないのも納得です。そもそも自分自身は若く見えているのだろうか…笑
Aging Clock(老化時計)
Aging Clock(老化時計)とは、生物学的年齢を測定または予測するために使用される用語です。老化の指標となるバイオマーカーが存在するという考えに基づいており、これを用いることで、暦年齢とは関係なく、個人の機能年齢を推定することができるといわれています。老化時計は加齢に関する研究や健康的な加齢を促進するための介入方法の開発に利用されています。もちろん、自分の健康や幸福を長期にわたって追跡し、改善するために個人も使用することができます(実際に利用している企業もある)が、今のところ、必ずしも正確ではなく、個人の生物学的な実年齢を必ずしも正確に反映しているとは限らないことに留意しなければいけません。この分野の研究はまだまだこれから発展していくのではないでしょうか。
なぜ老化スピードに個人差があるのか
老化のスピードに影響を与える因子は多岐にわたります。
- 運動
- 栄養
- 心(脳・睡眠)
- 環境
特に運動や栄養に関しては様々なところから情報が発信されているため、何かしらの効果があるのだろうとみなさんも知っているはずです。しかし、期待できる効果を理解できていないと、長期的に継続して実施することが難しいのではないでしょうか?せっかく良いことを実施していても3日坊主ではもったいないです。これらへ効果的に介入することで老化速度を遅らせることができ、健康長寿を全うできることにつながります。それぞれの項目に対しての詳細は、今後の記事にて発信していければと思います。一緒に勉強しながらアンチエイジングに効果的な介入を継続的に実施していきましょう。目指せPPK(ピンピンコロリ)
おわり
理学療法士の観点から、アンチエイジング、予防医学をとことん考えてみなさんに有益となる情報が発信できるように頑張ります!
ブログ初心者ですので、読みにくい部分もあるかと思いますがご容赦ください。
Horvath, S. (2013). DNA methylation age of human tissues and cell types. Genome Biology, 14(10), R115
日本抗加齢医学会(2023)「第4版 アンチエイジング医学の基礎と臨床」MEDICAL VIEW

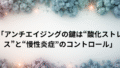
コメント